日本での試奏が可能です。 問い合わせ
ホセ・ラミレス二世、マドリッド、1928年 値下げしました 48万円
ホセ・ラミレス二世(小型ギター)、マドリッド、1955年 43万円
スペイン黄金時代の希少なクラシックギターたちです。
ギターが現代の形に近くなったのは、19世紀の末から20世紀の前半、
スペインのトーレスの功績が大きいとされています。
その弾き心地や鳴り方はまさに絶品、現代のわれわれにもリアリティを持って迫ってきます。
マヌエル・ラミレス工房(未亡人ラベル)、マドリッド、1917年頃 予価135万円
試奏動画1 試奏動画2


マヌエル・ラミレスはトーレスに次ぐ名声を持つギター製作家で、
セゴビアが1912年製の楽器を愛奏しています(製作はエルナンデス)。
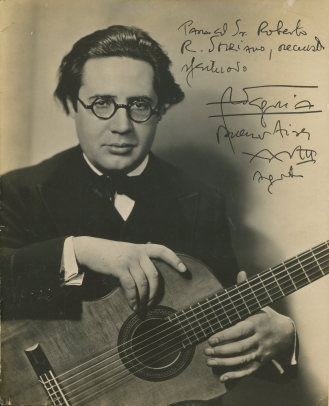
上:マヌエル・ラミレス作ギターを持つセゴビア
マヌエルは1916年に没しますが、その後も彼の工房で働いていた職人たち、
サントス・エルナンデスやモデスト・ボレゲーロらによりギターは製作され、
「マヌエル・ラミレス未亡人」のラベルで出荷されました。
このギターもそのような一台です。
やや小ぶりでチャーミングなギターです。弦長63センチ。
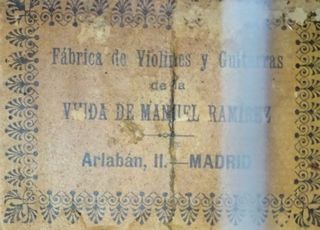
スプルースの表面板。ロゼッタには真珠貝の装飾。

ハカランダの裏横。

ヘッドには機械式糸巻きがつけられていた跡がありますが、
オリジナルのペグ仕様に復元されています。
ペグの使い勝手は良好です。

現状では超ローテンションのガットと巻き弦で張ってあります。
弾きやすく、音色は甘美。弾いていて愉しい楽器です。
日本で試奏できます。
ホセ・ラミレス二世、マドリッド、1928年頃 48万円
試奏動画1 試奏動画2

マヌエル・ラミレスの兄ホセ・ラミレスの息子ホセ・ラミレス二世の作品。
大型の堂々たるギターです。弦長65センチ。

この楽器とうり二つのギターがゴンドーラ/ワドラー著の『ギターのマスターピース』に載っています。
こちらは1927年製、ゴルぺ板が付いていますね。
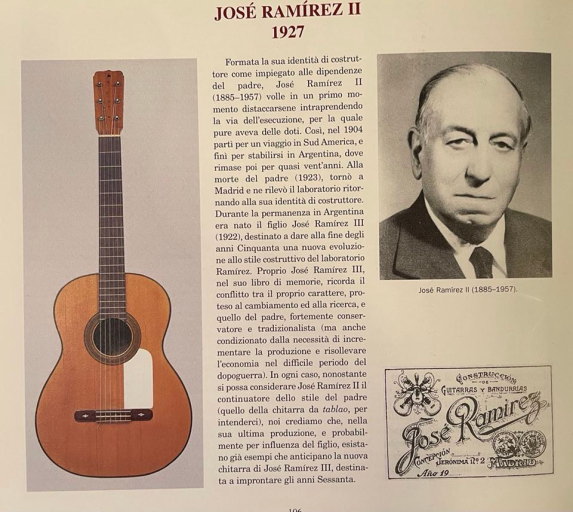
ラミレス二世のギターはバリオスも使っていました。
スプルースの表面板。
ブリッジの真珠母貝の装飾、ロゼッタも雰囲気のあるものです。

シープレスの裏横板。

軽く弾いてもはじける様に鳴る楽器で、
流石に名工ラミレスの作です。

ラミレス二世、マドリッド、1955年
価格43万円 試奏動画


こちらも名工ラミレス二世の手になるギター。弦長57.5センチの小型の楽器です。
いわゆるテルツギターのサイズですが、子供用の楽器だったのかもしれません。
いずれにしても、このサイズのスパニッシュギターは非常に希少です。

冬目の強いスプルースの表面板。

サイプレスの裏横板。

簡素な楽器ではありますが、さすがに名工ラミレスの楽器、弾き心地も鳴りも大層良いものです。
モダンのテルツを探している方、小型の名器を探している方にお勧めしたい楽器です。
戻る